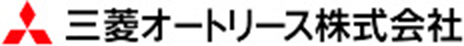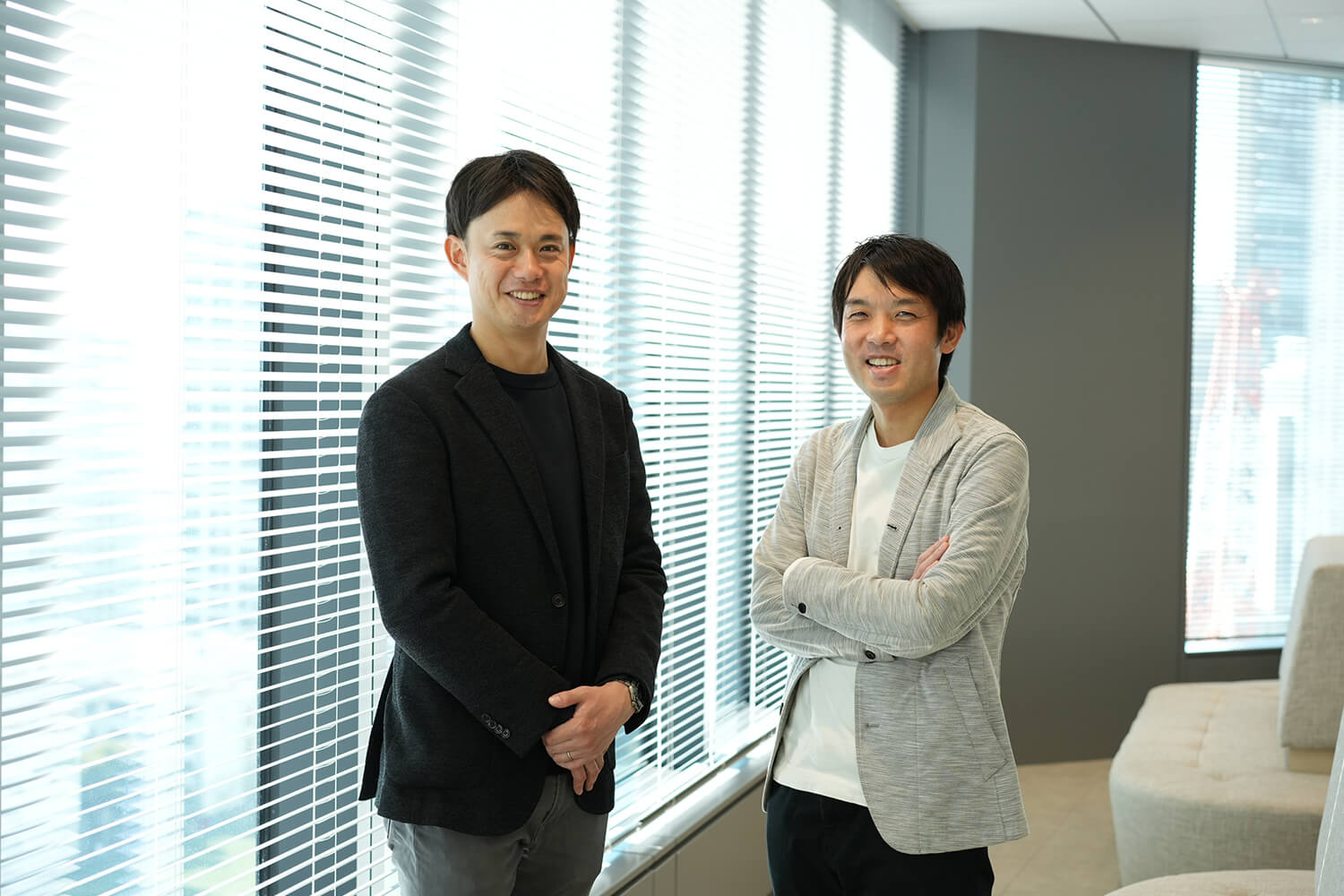Project member
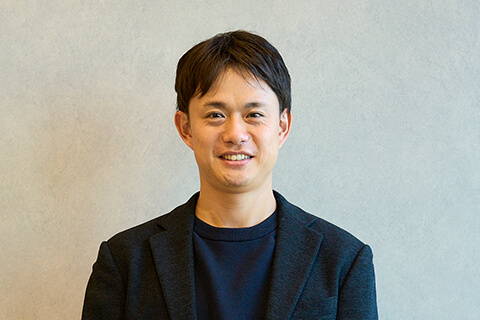
Y.I.
先進機能開発部先進機能開発課
2014年新卒入社
神奈川県出身で、学生時代はソフトテニス部に所属していた。休日は家族で出かけたり、動画配信サービスを視聴してリラックスしたりしている。
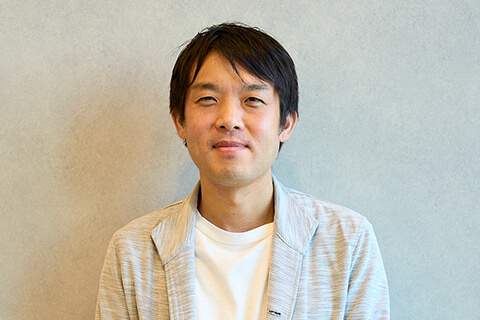
I.Y.
先進機能開発部先進機能開発課
2008年新卒入社
愛知県出身で、学生時代は陸上部に所属。現在もランニングを趣味としていて、フルマラソンで3時間切りを目指しトレーニング中。
Background
背景
求められる新たなモビリティサービス
2023年2月、三菱オートリースの先端機能開発部では、次世代フリートマネジメントサービスのビジネスプランの立案が行われていた。フリートマネジメントサービスとは、企業がビジネスで使う車両の利用・管理に関わる業務やコストを最適化し、適切な車両管理体制の実現をサポートする商材のことで、クルマにまつわるサービスが大きく変化する中、三菱オートリースも新たなフリートマネジメントサービスの組成を目指していた。
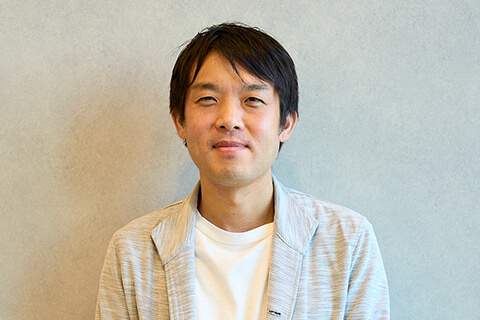
I.Y.
「三菱オートリースはこれまで、主に車両管理者(フリートマネージャー)向けに、クラウドやアウトソーシングのサービスを提供してきました。しかし、昨今のモビリティの多様化や働き方改革、DXの推進などにより、車両利用者(ドライバー)向けのサービスが求められるようになってきました。例えばアルコールチェックの義務化により、必要となる手続きや作成すべき書類・データが増えるなど、車両管理者だけではなくドライバーの業務も増加していたのです。まずは現場でどのようなサービスが必要とされているのかをヒアリングし始めました」
営業担当や顧客へのヒアリングを進めていくと、車両管理には複数のシステムやツールを使用しており、それぞれがバラバラであるため、管理が煩雑化しているという課題が多く聞かれた。車両の利用予約はA社のシステム、アルコールチェックはB社のクラウドサービス、日報の記録は手書きといった具合に、業務ごとに別々のツールを使用しているケースがあり、管理が複雑になってしまっていたのだ。それらのツールを一元管理することができれば、大幅な業務改善につながる。
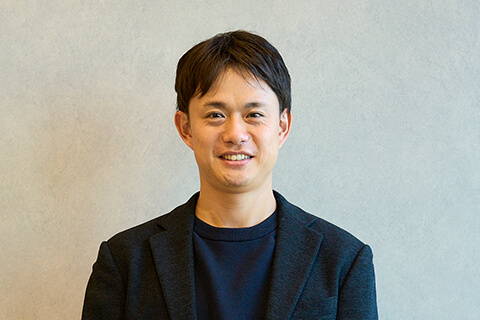
Y.I.
「もともと当社では、『MAL portal(マルポータル)』というWeb車両情報管理サービスを提供していました。しかしMAL portalは、主に車両管理者向けのツールであったため、ドライバーが必要とする機能が不足しておりました。ドライバーがスマホから手軽にシステムを利用し手続きを実行したり、もれなくデータを作成して一つにまとめたりするためには、新たなアプリケーションを開発する必要がありました」
三菱オートリースはウェブアプリケーションとして先述したMAL portalを有していたものの、これまで社内でネイティブアプリケーションの開発を行ったことはない。しかしながら、多くの顧客が求めていた次世代型サービス。三菱オートリースが目指す“モビリティサービス企業への進化”の実現のために、ドライバーや車両管理者を含めた、“移動するすべての人に向けたプラットフォーム”の開発計画がスタートした。
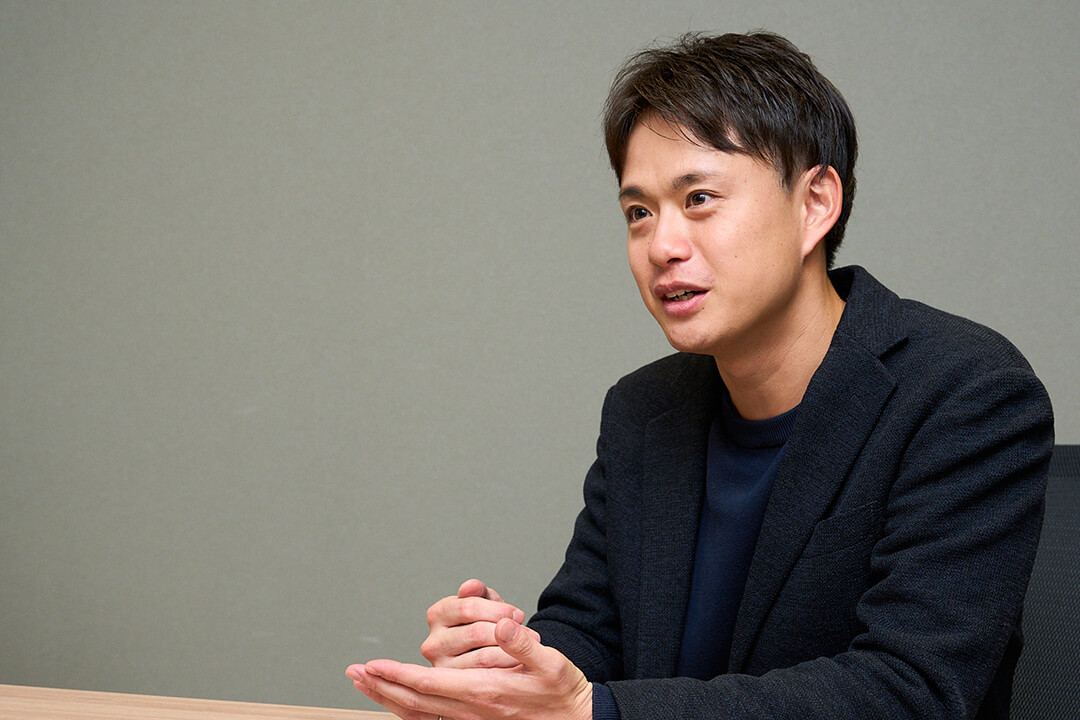

Process
プロセス
覚悟を決めて突き進む
自社内でのアプリケーション開発は、多額の予算を投入するプロジェクトであるため、慎重に議論が進められていた。当然、社内承認を得る難易度も非常に高い。内容の検討や、開発の実作業を担うパートナー企業の選定などを経て、取締役会に諮ることとなるが、それに向けても綿密な準備が求められた。
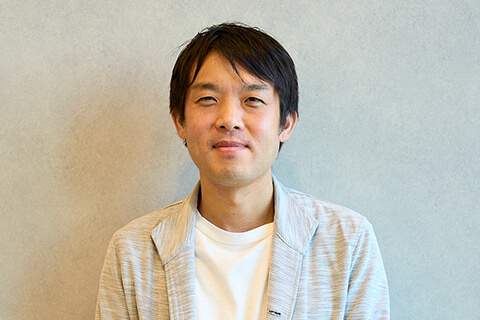
I.Y.
「まずはプロジェクト予算の算出が必要になりますが、パートナー企業へ私たちの要望を伝えるのも、非常に苦労しました。メンバーにアプリケーション開発を経験したことのあるメンバーがおらず、パートナー企業に対してどのような情報を、どの程度伝えれば良いのか、見当がつかなかったのです」
アプリケーションを開発するためには、まずアプリケーションに搭載する「機能要件」の整理に加え、操作性や動作速度などの「非機能要件」の整理が必要となる。正確な予算の算出には、正確な要件の整理が欠かせないのだ。パートナー企業のサポートを得ながら、顧客がアプリケーションを利用している姿を具体的にイメージし、要件へと落とし込んでいった。そして、開発にかかる全体コストを算出したうえで、社内承認を進めた。
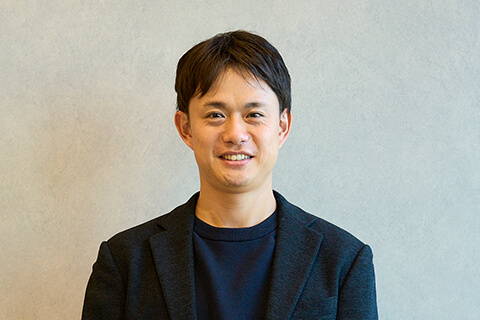
Y.I.
「オートリース企業において、システム開発やアプリケーション開発自体は珍しいものではありませんが、私たちが目指していた“移動するすべての人に向けたプラットフォーム”が、実際にどれほど必要とされるのかは未知数で、その重要性を説かなければ社内承認を得ることはできません。営業部門にも協力を依頼し、お客様へのヒアリング結果を取りまとめて定性的なデータの収集にあたりました。また、MALが当アプリケーションを有する場合と、有さない場合とで顧客数やリース契約数の推移予想マップを作成し、定量的な情報も取り揃えました」
しかしながら、社会情勢や自動車を取り巻く環境が刻々と変化する中で、未来を確実に予測することは困難である。I.Y.もそれは理解していた。
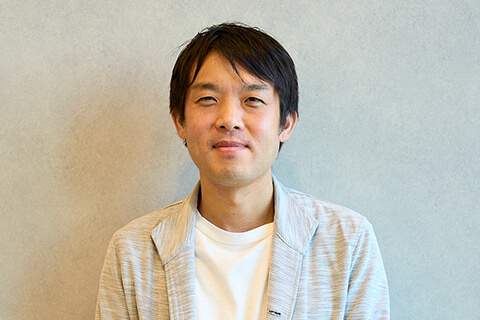
I.Y.
「データは確かに不可欠な情報ですが、あくまで予測に過ぎません。最後は、『自分たちが責任を持って開発を行い、モビリティサービス企業への進化に貢献するんだ』という覚悟を持つことが大切だったと思います。大きなコストがかかるプロジェクトですので不安もありましたが、腹を括って堂々と提案できたことで、無事に社内承認が得られたと思っています」
将来は不確実であるため、どれだけデータを集めて議論をしたとしても、“絶対”はない。それでも未来を切り開いていくためには、次世代型のサービスは欠かせないと確信していた。最後に拠り所となったのは、メンバー一人ひとりの覚悟だった。このプロジェクトを必ず成功させてみせる——。いよいよ、本格的なアプリケーション開発の段階に入っていった。


Result
成果
関係各所を駆け回る
山場を超えた先端機能開発部のメンバーたちだったが、開発を進めていく中でも壁にぶつかる。社内承認後、より詳細な要件定義を詰めていく段階で、当初は予定していなかった機能が追加で必要になるなど、想定外の出来事が頻繁に発生。リリースの日程が決まっている中で、スケジュールを遅らせるわけにはいかない。Y.I.はその度に、協力会社と社内の調整に奔走した。
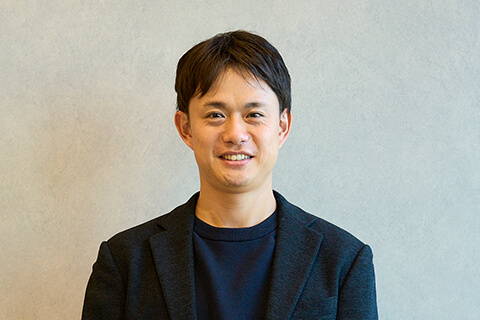
Y.I.
「私は以前、フリートマネジメントサービスの営業を行っていたため、『お客様がアプリケーションを利用した際に、どんな機能があれば利用しやすいか』という観点で、開発を進めていました。顧客目線は必要不可欠ですが、一方で、アプリケーションを運用する私たちの使い勝手も考慮しなくてはなりません。そうした視点は、要件定義を進めていく中で初めて気づかされました。変更が必要になる度にパートナー企業と連携し、アプリケーションに落とし込んでいきました」
またユーザーがアプリケーションを利用する際の、ボタンの配置やテキストサイズ、ページの遷移方法など、専門的な内容についても、自分たちで決めていかなければならなかった。プロジェクトメンバー間で意見が異なることも多々あった。日々難局が訪れるものの、プロジェクトメンバー全員が、一貫して「お客様にとってどのようなサービス・システムがベストなのか」を考え抜くことで、乗り越えてきた。
その過程で、アプリケーションの名称が決まった。その名は「MAL mobi(マルモビ)」。アプリケーションのベースとなったMAL portalから着想を得て、候補案をいくつか提示したうえで社内アンケートを実施。三菱オートリースはモビリティサービス企業を目指している最中であり、アプリケーションは「モビリティの管理や利用をまるごとDX」というコンセプトを掲げていることから、「MAL mobi」が採用された。
協力会社によるプログラミング開発、リリーステストを経て、2025年2月にMAL mobiの利用が始まった。


Future
未来
ここからがMAL mobiのスタート
煩雑な作業に追われる車両管理者やドライバーは、アプリケーションを活用することで、ワンストップでアルコールチェック、運行日報の記録、車両管理などをできるようになった。顧客からは、今後のさらなる機能追加を期待する声も挙がっている。
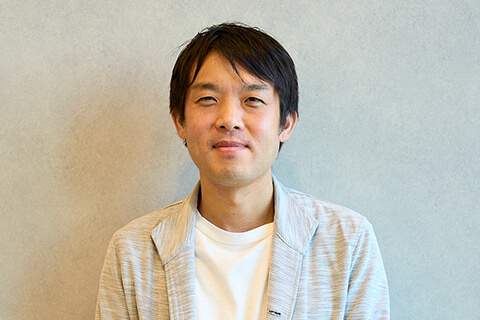
I.Y.
「MAL mobiをリリースすることで、このプロジェクトが終了となるわけではありません。より良いアプリケーションを目指し、次期開発の検討も進めています。例えばカーシェアの予約や、スマホ決済ができるような機能を追加したり、テレマティクスの運行データの取得や日報の自動作成ができるようになったりすると、より便利なツールになっていくのかなと考えています。MAL mobiはまだまだ生まれたばかりのアプリケーションなので、これからもっと成長させていきたいですね」
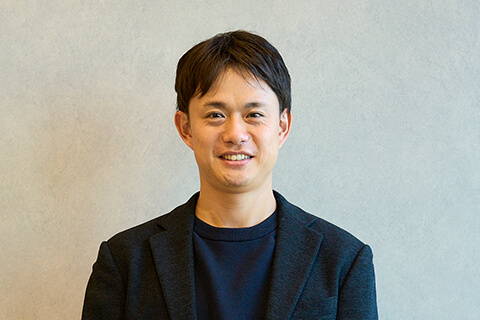
Y.I.
「これまでは営業などお客様に近い立ち位置での仕事が多かったのですが、このプロジェクトに携われたことで、『商品やサービスを生み出す立場』での経験を積むことができました。アプリケーション開発という未知の領域での業務でしたが、チームメンバーやパートナー企業と協力しながら、一つひとつ壁を乗り越えることができました。何もないところから、サービスが形となっていく達成感はかけがえのないものです。お客様がより使いやすいモビリティサービスにできるよう、検討を進めていきます」
三菱オートリースの新たな挑戦は始まったばかり。MAL mobiはこれから、さらなる進化を遂げていく。